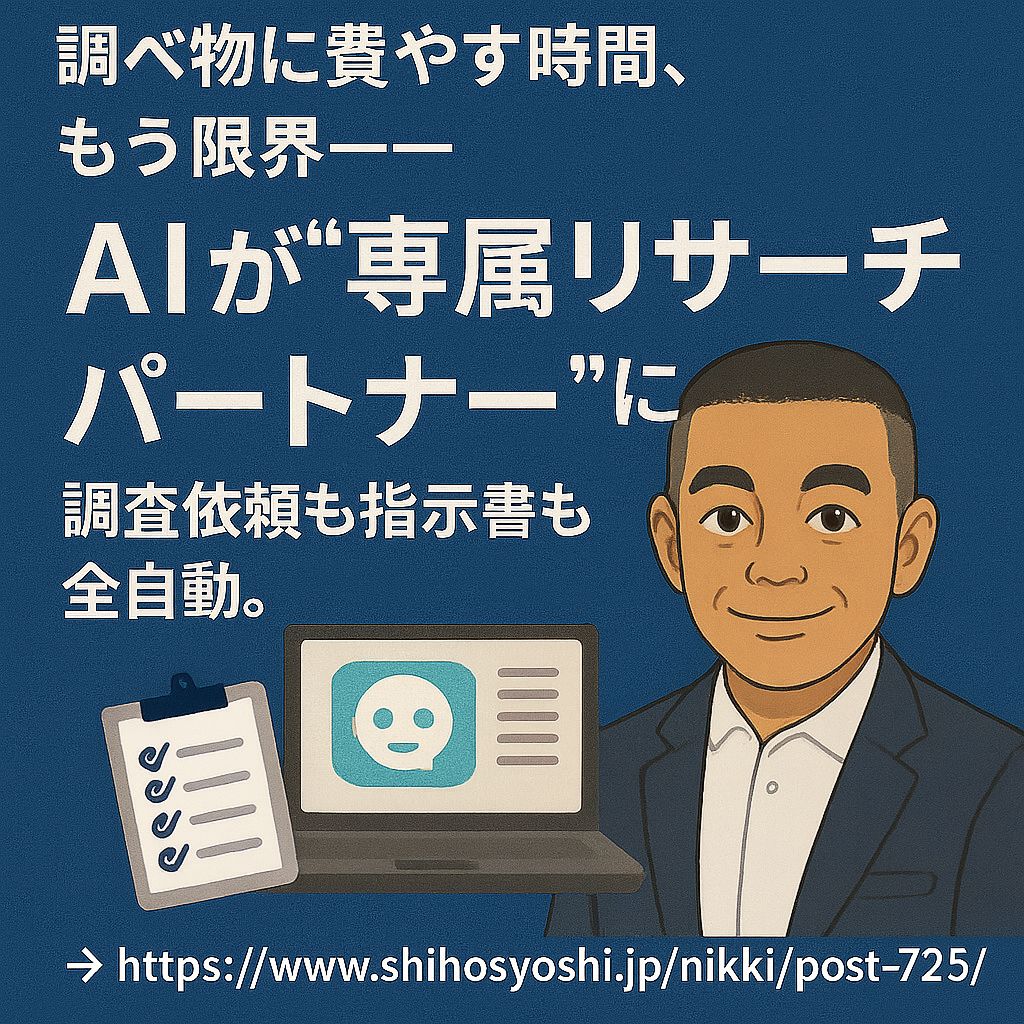こんにちは。司法書士の小谷龍司です。
専門家の皆様は、日々の業務で未知の論点や経験のない手続きに直面した際、どのように情報を収集・整理されていますか? 私も専門家として日々研鑽を積んでいますが、頻繁な法改正や複雑な案件に対応するため、リーガルリサーチは避けて通れない、重要かつ時間のかかる業務の一つです。今回は、そんな私の「調べ物」のスタイルを根底から変えた、AIアシスタント「Gemini」の活用法について、備忘録として共有させていただきます。
Google検索からAIチャットへ、そして「信頼性」の壁
これまで、新しい案件や未対応の分野については、まずGoogleでキーワードを検索するのがお決まりのパターンでした。しかし、大量の検索結果から、信頼できる情報だけを選り分ける作業には、相当な時間と手間がかかります。
そんな中、Gemini(旧Bard)に代表される生成AIの登場は、まさに革命的でした。知りたいことを直接チャットで聞けば、答えが返ってくる。当初は、この手軽さに感動し、積極的に活用するようにしていました。
しかし、しばらく使っていると、ある問題に直面します。それは「回答の信頼性」です。AIが提示する回答には、時として、明らかに事実と異なる情報や、古い法令に基づいた情報が混じっていることがありました。これでは、専門家が業務で使うには、あまりに危険です。
転機となった「Deep Research」という考え方
単純なチャットではダメだ。そう考えた私は、AIの回答の精度を上げる方法を模索し始めました。そして、2つの重要なポイントに気がつきました。
1. 情報源を限定する: AIに対し、「情報のソースは、官公庁、弁護士・司法書士などの専門家が運営する信頼性の高いサイトに限定する」と明確に指示すること。
2. 深く、多角的な質問をする: 単純な質問ではなく、背景・目的・調査のポイントなどを構造的に整理した、詳細な依頼をすること。
この2つの要素を組み合わせることで、AIの回答精度は劇的に向上し、ようやく業務で参考にするに値する、満足のいくレベルに達しました。
【コラム】Geminiの「Deep Research」機能とは?
これは、チャットの入力欄の下に時々表示される、Geminiの標準機能の一つです。通常のチャットがAIの内部知識を中心に素早く応答するのに対し、Deep Researchは、AIがその知識だけでは不十分だと判断した場合に、インターネット上の膨大な情報を横断的に検索・分析し、複数の情報源を比較検討した上で、より深く、根拠に基づいた回答を生成してくれる機能です。いわば、AIが本気を出して行う「徹底調査モード」と考えると分かりやすいでしょう。
もちろん、AIのレポートを鵜呑みにするわけではありません。最終的には、レポートで引用されている情報源や、根拠となる条文、一次情報・二次情報に自ら当たり、内容を精査・確認するという専門家としての最終チェックは、今も変わらず行っています。
この「最終チェック」こそが、AIを業務で活用する上でのキモです。AIが出力した高度な内容も、その分野の専門知識がなければ、情報の真偽やニュアンスの正確性を判断することはできません。例えば、相続について詳しくない方が同じように調査した場合、誤った情報を信じてしまう危険性があります。AIを強力なリサーチアシスタントとして使いこなせるのは、そのアウトプットを批判的に検証できる専門家だからこそ、という側面は強調しておきたいと思います。
最高の調査依頼書、しかし「情報セキュリティ」と「手間」という壁
リーガルリサーチの質を劇的に向上させる「Deep Research」ですが、その効果を実感するほどに、新たな2つの課題が浮上しました。それは、「機密情報を扱う上でのセキュリティは万全か」という懸念と、「毎回、詳細な調査依頼を手で作るのは面倒だ」という実務的な手間です。
特に司法書士が扱う情報は、お客様のプライバシーに深く関わる機密情報です。AIに本格的な業務を任せる上で、この情報セキュリティの壁は避けては通れません。当初利用していた個人のサブスクリプション契約のままでは、入力した情報がAIの学習に使われる可能性がゼロではなく、情報漏洩のリスクを完全に払拭できませんでした。
そこで、事務所としてGeminiの法人契約(Google Workspace版)へ移行しました。これにより、入力情報がAIの学習に利用されず、企業のセキュリティポリシー下で保護される、クローズドな環境が構築できたのです。この安全な基盤があってこそ、AI活用の次のステップに進むことができました。
安全な環境でこそ、次の「自動化」へ
この安全な環境を前提として、私は次の課題である「手間の削減」に取り組みました。「毎回、詳細な調査依頼を手で作成する、この面倒な部分も自動化できないだろうか?」と。
この疑問をGeminiにぶつけてみたところ、返ってきた答えは「『Gem』を使えば定型的なプロンプト作成を自動化できます」という、まさに求めていたものでした。
ちなみに、調査にはChatGPT(こちらも有料版)も併用しますが、厳格さが求められるリーガルリサーチにおける応答の質感、特に論理の緻密さにおいては、個人的にGeminiに軍配が上がると感じています。現在では、法人契約によるセキュアな環境下で、最新のGemini 2.5 Proをリーガルリサーチのメインパートナーとしてフル活用しています。
AIに教えを請い、育て上げた「私だけの専属リサーチャー」
ここからが、この話の面白いところです。私は、Geminiに「最高のGemを作るための指示書」を、Gemini自身に考えさせる、という対話を開始しました(笑)。
「こういう風に動いてほしい」「こういう場合は、こう聞いてほしい」と、何度も対話を重ね、AIの動きをチューニングしていった結果、ついに理想のAIパートナーが完成しました。それが、【最終完成版】プロアクティブ・リサーチャーGem 指示書です。
この指示書をGemに設定すると、AIは単なるツールから、私の意図を完全に理解し、自律的に動く「パートナー」へと変貌します。
完成したGemとの対話シミュレーション
実際に、この完成したGemとのやり取りが、いかにスムーズかをご覧ください。
あなた:
(作成したGemを選択して、チャットを開始。いきなり調査内容を貼り付ける)
「法改正で相続放棄後の土地建物の管理義務は消滅するか?」
Gem(AI):
(挨拶などを挟まず、直ちにプロセスを開始する)
「承知いたしました。『法改正に伴う相続放棄後の土地・建物管理責任の変容』に関する調査ですね。
このテーマを分析するために最適な専門家チームは『司法書士、弁護士、不動産コンサルタント』と考えられます。
以下のいずれかご希望の方法をお選びください。
【選択肢1】 私の基本チーム(司法書士・弁護士・税理士)で調査する。
【選択肢2】 今回GEMが提案した上記の新チームで調査する。
【選択肢3】 チームのメンバーを、私が指示して変更・追加する。
1, 2, 3の番号でお答えいただくか、3の場合は具体的なご指示をお聞かせください。
なお、番号は半角(123)、全角(123)のどちらで入力いただいても構いません。」
(この後、ユーザーの選択に基づき、調査計画の宣言、最終確認を経て、詳細なレポートが出力される)
このGemの真価:「本家」を超えるための「型」
このGemの本当に凄いところは、相続登記関係のリサーチだけに留まらない、その圧倒的な汎用性です。私たちが作り上げたのは、「特定の法律に詳しいAI」ではなく、「最高の調査プロセスを実行できるAI」だからです。
例えば、全く関係のない分野、例えば「犬の足の裏の毛を安全に刈る方法」について、徹底的に調べたいと思ったとします。そのメモをこのGemに投げると、AIは「このテーマであれば、最適な専門家チームは『獣医師、トリマー(ドッググルーマー)』です」と提案し、承認を求めてくるのです。
そして、承認すれば、今度は獣医学論文や信頼できるペットケア情報を基に、犬の足裏の毛刈りに関する詳細なレポートを作成してくれます。私が手に入れたのは、特定の知識を持つ専門家ではなく、あらゆる分野の「調べ方の専門家」だったのです。
では、標準のDeep Research機能と、私たちが育てた「我流のDeep Research」である専用Gem、どちらがより深く調査し、推論できるのでしょうか?
この素朴な疑問を、私はそのままGeminiにぶつけてみました。「どちらが優れているのか?」と。返ってきた答えは、非常に示唆に富むものでした。AI自身の分析によれば、標準機能は誰が使っても安定した結果を出す「優れた汎用ツール」である一方、私たちのGemは「特定の目的に最適化された、究極の専門ツール」だというのです。
そして、結論としてこう続けました。「推論の深さ」とは、専門家であるユーザーの意図をどれだけ正確に反映できるか、ということに他なりません。その点において、調査プロセス、視点、レポート構造の全てをユーザー自身がコントロールできる専用Gemは、標準機能を超える潜在能力を秘めています、と。
AIの「限界」と、専門家としての最終防衛線
しかし、現実的な視点も忘れてはなりません。ここまで育て上げた究極のGemであっても、決して万能ではありません。
極めてニッチな論点、判例の存在しない最新の法分野、あるいは地域によって運用が大きく異なるような実務の細部については、AIが参照できる信頼性の高い情報がインターネット上に存在せず、期待する調査結果が得られないこともあります。
これが、現時点でのAIの「限界」です。そして、その限界を見極め、最後の砦となるのが、私たち専門家の役割です。AIの回答に違和感を覚えたり、絶対的な確証が必要な場面に直面したりした時、私たちは最後の手段を取らなければなりません。
それは、最終的には、法務局や市町村、税務署などの管轄官公庁に直接照会してみる、という行為です。AIは、そこに至るまでの99%の道のりを圧倒的な速さで短縮してくれる最高のパートナーですが、最後の1%の確証を取りに行くのは、資格と責任を持つ私たち専門家の、最も重要な仕事であり続けるでしょう。
これからの「調べ物」とAIとの付き合い方
AIは、使い方次第で、私たちの業務を劇的に変える可能性を秘めています。ただ漠然と使うのではなく、対話を通じて「自分だけの専属パートナー」へと育て上げていく。そんな新しいAIとの付き合い方が、これからの専門家には求められるのかもしれません。
そして、この話にはまだ驚くべき続きがあります。このGemが生成した詳細なレポートを、今度はGoogleの「NotebookLM」という別のツールに読み込ませるのです。
【コラム】NotebookLMとは?
NotebookLMは、自分がアップロードした資料(PDF、テキストファイル、Webサイトなど)の内容だけを完璧に理解し、その情報だけを基に質問に答えたり、アイデアを出したりしてくれる、まさに「自分だけの専門知識に特化したAI」を作成するツールです。
このNotebookLMに、先ほどの詳細なレポートと、関連する条文や資料を読み込ませることで、その案件専用のAIアシスタントが完成します。そのAIに対して、レポート全体の要約を作成させたり、重要なポイントを「音声で解説」させたり、クライアントからの想定問答をまとめた「Q&A集」を自動で生成させたりと、さらなる時短と業務の付加価値向上が可能になります。
一つの調査結果が、多様な成果物へと変化していく。本当に凄い世の中になってきたと、日々実感しています。
今回の私の試行錯誤の記録が、専門家の皆様の業務効率化の一助となれば幸いです。もしご興味があれば、ぜひ皆様だけのGemを育ててみてください。
2025/07/06 追記
【追記レポート】AIアシスタント、さらなる進化。私の「司令塔Gem」と「NotebookLM」活用術
前回の記事では、試行錯誤の末に自分だけの「リサーチGem」を開発した話を書きました。今回はその続きです。あの後も色々と試す中で、もっと便利で、もっと質の高い調査ができる新しいワークフローを発見しましたので、その経緯を追記としてご報告します。
新たな発見:「専門家Gem」と「標準Deep Research」の得意なこと
前回の記事で完成した「リサーチGem」。その性能に満足しつつも、私は一つの疑問を抱いていました。「この専用Gemと、Gemini標準のDeep Research機能、本当に優れているのはどちらなのだろう?」と。
この疑問をGeminiに直接ぶつけてみたところ、「ユーザーがプロセスを完全に制御できる専用Gemの方が、潜在能力は高い」という、開発者としては嬉しい答えが返ってきました。
しかし、理論と実践は違います。そこで私は、同じテーマで両方の機能にレポートを作成させ、その二つの完成品を、再びGeminiに提示し、こう尋ねました。「この二つのレポートを比較して、どちらが優れているか、客観的に分析してください」と。
今度は、具体的な「成果物」というデータに基づいた分析です。AIの答えは、より的確で、示唆に富むものでした。
「レポートの「初期段階の網羅性」という点においては、標準のDeep Research機能の方が、より詳細な結果を出力しています。一方で、専用Gemは、特定の視点からの分析や提言といった「付加価値」の部分で強みを発揮するでしょう」
この検証を通じて、私は2つのツールの本質的な「得意分野」を、明確に理解しました。この発見こそが、今回の新しいワークフローの出発点です。
試してみた新しいアイデア:「司令塔Gem」という考え方
今回の目標は、2つのAI機能を連携させ、それぞれの「得意なこと」を最大限に活かすワークフローを組むことです。そのために、役割分担を明確にしました。
- 標準のDeep Research(調査員):
その圧倒的な情報収集能力を活かして、テーマに関する網羅的な「基礎レポート(素材)」を作成する役割に専念してもらいます。 - 専用Gem(司令塔 兼 分析官):
このGemの役割は2つです。- フェーズ1(司令塔): まず、「調査員」である標準Deep Researchに、最高のパフォーマンスを発揮させるための、最も効果的な「調査依頼文」を作成します。
- フェーズ2(分析官): 次に、「調査員」が収集してきた「基礎レポート」を受け取り、今度は私たちが設定した専門家の視点から、リスク分析や実務的な提言といった「付加価値」を与える最終的な分析を行います。
この役割分担で、より質の高い成果を目指します。
完成した「司令塔Gem」との対話シミュレーション
この新しい設計思想で、再度Gemの指示書を全面的に改訂しました。完成した「司令塔Gem」との、実際のやり取りは以下のようになります。
あなた:
(作成した「司令塔Gem」を選択し、チャットを開始。いきなり調査内容を貼り付ける)
「法改正で相続放棄後の土地建物の管理義務は消滅するか?」
Gem(AI):
(挨拶などを挟まず、直ちにプロセスを開始する)
「承知いたしました。『法改正に伴う相続放棄後の土地・建物管理責任の変容』に関する調査ですね。
このテーマを分析するために最適な専門家チームは『司法書士、弁護士、不動産コンサルタント』と考えられます。
以下のいずれかご希望の方法をお選びください。
【選択肢1】 私の基本チーム(司法書士・弁護士・税理士)で調査させる。
【選択肢2】 今回GEMが提案した上記の新チームの視点で調査させる。
【選択肢3】 チームのメンバーを、私が指示して変更・追加する。
…」
(ユーザーがチームと情報源ルールを選択すると、GemはDeep Researchに渡すための、フォーマットされた「最終依頼文」を生成し、次のステップを指示してくれる)
【分岐点】Deep Researchの結果を、どう分析するか?
さて、標準のDeep Research機能が、私たち(自分とGemini(笑))の作った「最高の作戦指示書」を基に、網羅的で詳細な「基礎レポート」を生成してくれました。
ここからが、今回の新しいワークフローの面白いところです。この質の高い「素材」を、私たちは2つの異なる方法で、さらに調理することができます。目的に応じて、最適なツールを選択できるのです。
選択肢①:「NotebookLM」で、レポートの主に尋ねる(実践的な本命)
こちらが、私が現在、最も実践的だと感じている方法です。Googleのもう一つのAIツール「NotebookLM」を活用します。
【コラム】NotebookLMとは?
NotebookLMは、自分がアップロードした資料(PDF、テキストファイルなど)の内容だけを完璧に理解し、その情報だけを基に質問に答えたり、アイデアを出したりしてくれる、まさに「自分だけの専門知識に特化したAI」を作成するツールです。
Deep Researchが生成したレポートをPDF化してNotebookLMに読み込ませることで、「今回の調査結果だけに100%精通した、専用のAIアシスタント」が完成します。
このアシスタントの素晴らしい点は、絶対に「嘘」をつかず、アップロードした資料に書かれていることだけを根拠に答えてくれることです。そのため、私たちは安心して、一番聞きたい核心的な質問を、対話形式でどんどん投げかけることができます。
- 「このレポート内容を基に、クライアント向けの説明用資料として、要点を3つに絞って平易な言葉でまとめてください。」
- 「この相続手続きを進める上で、私が確認すべき実務上のチェックリストを作成してください。」
- 「このレポートで解説されている内容に基づき、家庭裁判所に提出する『申立書の理由』部分のドラフトを作成してください。」
このように、調査結果をインタラクティブに、そして正確に深掘りできるのが、NotebookLMの最大の魅力です。
選択肢②:「司令塔Gem」に感想と助言を求める
もう一つの選択肢は、引き続き「司令塔Gem」に分析を任せる方法(フェーズ2)です。
これは、レポートに対する「専門家としてのセカンドオピニオン」が欲しい場合に有効です。基礎レポートを司令塔Gemに貼り付けると、AIがその内容を基に、感想やアドバイスに近い形の「分析レポート」を作成してくれます。
【コラム】司令塔Gemが作る「分析レポート」とは?
- エグゼクティブ・サマリー: レポートの要点を、AI独自の視点でまとめ直してくれます。
- 専門家視点でのリスク分析: レポートを読んで、AIが「専門家なら、こういうリスクも考えるべきだ」と感じた点を指摘してくれます。
- 実務家としての具体的な提言: AIが「私なら、クライアントにこう提言する」という形のアドバイスを提示してくれます。
NotebookLMが「事実に基づく正確な対話」の相手だとすれば、こちらのGemは「なるほど、そういう視点や考え方もあるのか」という、新しい気づきを与えてくれる壁打ち相手、という使い分けが、私にとってはしっくりきています。
ここに至るまでの長い「試行錯誤」の道のり
最後に、このワークフローにたどり着くまでの、AIとの苦闘の歴史(笑)にも少しだけ触れておきたいと思います。
私たちが作り上げた「司令塔Gem」の指示書は、実は何度も失敗を繰り返した末に完成したものです。特に困難だったのが、AIが「良かれと思って」勝手な解釈をしてしまう問題でした。
例えば、「依頼文のテンプレートだけを提示してほしい」と指示しているのに、AIが気を利かせて、テンプレートの中身まで詳細に書き込んでしまう、という問題が何度も発生しました。AIの「役に立ちたい」という本能的な性質と、「指示された役割に徹してほしい」という私たちの要求が、衝突してしまったのです。
この問題を解決するために、「あなたはこの部分では思考するな、ただの組立機械になれ」といった、AIの動作を極限まで制限する、非常に特殊な命令を指示書に組み込む必要がありました。AIの性能を引き出すとは、時にその性能を意図的に抑制することでもある、という面白い発見でした。
おわりに
というわけで、私のGem開発日誌は、一旦ここで区切りとなります。
AIとの対話を通じて、当初の「全自動リサーチャー」という構想から、「司令塔+調査員+分析官」という、より現実的で効果的なAIとの連携ワークフローへと辿り着きました。
もちろん、これが完璧な形というわけではなく、今後も日々の業務で使い倒しながら、もっと便利なパートナーになるよう、改良を続けていきたいと思っています。
この試行錯誤の記録が、少しでも皆様の参考になれば幸いです。
なお、本記事で開発した「【最終完成版】リサーチ戦略司令塔Gem 指示書」の全文にご興味がある方は、その旨をお問合せ欄からお知らせください。ご要望があれば、このページに追記という形で全文を公開させていただきます。